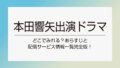NHKドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に登場する徳川家治(とくがわ・いえはる)は、実際にはどのような人物だったのでしょうか?ドラマでは優しく理知的な将軍として描かれていますが、史実の家治像と違いはあるのでしょうか?
この記事では、徳川家治のプロフィールや功績、人柄をわかりやすく解説し、ドラマとの違いや演出の意図にも迫ります!
この記事を読んでわかること
- 徳川家治の史実に基づく人物像
- 家治の治世や功績、性格について
- ドラマ『べらぼう』での描かれ方との違い
- 家治と田沼意次・蔦屋重三郎との関係性
徳川家治とはどんな人?史実での人物像は?
プロフィール(生没年・家系・在位など)
徳川家治(とくがわ いえはる)は、江戸幕府の第10代将軍です。生まれは1737年(元文2年)、亡くなったのは1786年(天明6年)で、享年50歳でした。
有名な8代将軍・徳川吉宗の孫であり、9代将軍・徳川家重の嫡男として生まれました。
父・家重は言葉が不自由だったとされており、そのため家治は幼少期から祖父・吉宗に特に目をかけられ、帝王学を直接教え込まれたといわれています。
なんと元服は4歳という異例の早さで、当時の朝廷からは権大納言に叙任されるなど、非常に将来を期待された存在でした。
将軍在位期間は1760年(宝暦10年)から1786年(天明6年)までの26年間。
幕府の中ではやや目立たない存在ですが、史実を辿ると興味深い人物像が浮かび上がってきます。
将軍としての功績や政策
将軍として大きな政治改革を行ったわけではありませんが、家治は「質素倹約」において祖父・吉宗以上に厳しく取り組んだ人物でした。
とくに大奥の経費削減に力を入れ、従来からさらに約3割のコストカットを実現したとされています。
政治面では、実務の多くを側近である田沼意次に任せ、自身は趣味や文化活動に力を入れるスタイルをとっていました。
結果として、田沼の時代に経済面ではある程度の成果が出た一方、賄賂や腐敗の温床となったという評価もあります。
目立った改革や戦はなく、「平穏な時代を維持した将軍」として語られることが多いのも、家治の時代ならではの特徴です。
徳川家治は将軍としての評価が低めですが、この頃には有能な干渉が実験を握り、将軍自体は政治を直接動かすようなことが無く象徴的な存在として君臨していたと言われています。
人柄や評価(性格・学問好きなど)
徳川家治は、文武に秀でたバランスのとれた人物だったと言われています。とくに書画に優れ、趣味は鷹狩りや将棋。将棋はかなりの腕前だったようで、対局にも熱心だったことが記録に残っています。
また、祖父・吉宗を深く尊敬しており、食事や生活様式なども吉宗に倣うなど、意識的に同じ道を歩もうとした姿勢が見受けられます。
吉宗の理想をなぞるかのような行動は、彼が祖父に認められたい、という強い思いの表れだったのかもしれませんね。
私生活では非常に愛妻家として知られ、正室の倫子(ともこ)とは仲が良く、側室を迎えることには消極的でした。子が女子ばかりであったことから田沼意次に勧められて仕方なく側室を迎えましたが、その後もあまり側室のもとには通わなかったようです。
子供達は短命で後継には恵まれなかった
子供たちは短命でした。
- 側室:蓮光院
長男:徳川家基(1762年 – 1779年) - 側室:養蓮院
次男:貞次郎(1762年 – 1763年)
次男の貞治郎はわずか1歳で亡くなっています。
側室の蓮光院は属名を「知保」といいます。
倫子の産んだ千代姫は1歳、次女の万寿姫は13歳で他界しています。
知保の産んだ世継ぎの徳川家基は18歳で亡くなってしまい、徳川家斉(第11代将軍)を養子に迎えています。
家治には異母弟清水重好(清水徳川家初代当主)がいましたが、後継者となる子供はいません。
この頃子供を大人にするのはとても大変だったことが伺われますね。
家治は晩年は脚気が悪化し心不全で亡くなったとされますが、
一部では田沼の陰謀による毒殺説もあります。ただし、家治の死後、田沼は急速に失脚しており、毒殺の可能性は低いと考えられています。
『べらぼう』の徳川家治はどんな人?
ドラマ『べらぼう』に登場する**徳川家治(とくがわ いえはる)**は、江戸幕府の第10代将軍。穏やかで人情味のある性格ながら、将軍としての重責と日々向き合う人物として描かれています。彼の特徴を理解するには、腹心の家臣・田沼意次(たぬま おきつぐ)との関係性に注目するのがポイントです。
べらぼうでの徳川家治の描かれ方
べらぼうは蔦重こと蔦屋重三郎の生涯を描いている物語です。
基本は吉原や庶民の生活に根付いた話であり、江戸幕府の話は庶民文化の時代背景となる部分。
家治亡き後の後継者家斉や老中が田沼意次から松平定信となり庶民の暮らしは「質素倹約」娯楽を含む風紀取締りも厳しくなるという時代背景が描かれることになります。
べらぼうでは蔦重と直接関わりがあったのは田沼意次であり家治は直接会うこともなく退場になりそうな感じです。
田沼意次とは深い信頼関係で結ばれている
家治と田沼意次の関係は、単なる将軍と老中という立場を超えた、信頼と協力のパートナーシップにあります。ドラマでは、家治が自ら人形芝居の黒子役を田沼に任せる場面も描かれ、両者の気心知れたやり取りが印象的です。
田沼の進言に耳を傾け、時に政敵とも協力して改革を進める姿からは、柔軟性と聡明さを備えた将軍像が浮かび上がります。実際、田沼の財政政策に賛同し、倹約によって幕府の蓄えを回復させたのも家治の判断でした。
理想と現実の間で揺れる将軍
一方で、家治は時に「理想を優先するあまり、周囲との摩擦を招く」一面も見せます。たとえば、家臣たちが日光社参の負担を懸念する中でも、「家基の願いだから」と実施を決めてしまう場面は、情に厚いが、政治的バランスに悩む一面を感じさせます。
さらに、息子・家基が急死した後にはそのショックから政治への関心を失いかけ、心を病みかけるなど、人間的な弱さも赤裸々に描かれているのが『べらぼう』の家治の魅力でもあります。
民を思う優しき将軍像
家治は、財政難に苦しむ庶民の実情にも目を向けています。田沼が座頭金の不正を告発した際には、民の苦しみに共感し、厳しい取り締まりを命じるなど、民思いの将軍としての決断力も見せます。
特に、強引に家を乗っ取られた庶民の声に耳を傾け、「徳川家が庶民を苦しめてはならぬ」と厳しい態度を示した場面では、為政者としての矜持と責任感がうかがえます。
息子を失い、孤独と向き合う晩年
家治が最も信頼していた息子・家基が鷹狩り中に急死するという大事件が起こります。家治は事件の真相を追い求めながらも、真犯人の影に迫ることができず、さらに信頼していた側近・松平武元までをも失うことになります。
この悲劇を通して、家治は政治の闇に深く傷ついた孤独な将軍像へと変わっていきます。亡き妻に似た女性を側室に迎えるという決断は、そんな心の隙間を埋めようとする人間らしい苦悩の表れでしょう。
徳川家治ドラマと史実の違いとは?
基本的には、ドラマの家治と史実の家治に大きな違いはありません。
ただし前の項でも説明した通り、徳川家治は愛妻家で、御台所の倫子(ともこ)を深く愛した人物です。側室は2人だけで、その2人に子ができたあとは、あまり足を運ばなくなったとされています。以降、新たな側室を迎えたという記録も残っていません。
一方ドラマ『べらぼう』では、亡き妻に似た女性を側室に迎えるという描写があります。
これは家治の“人間らしい弱さ”や“孤独”を表すための創作要素と考えられます。
実在の家治には見られない部分ではありますが、ドラマとしての人物描写を豊かにするための演出ともいえるでしょう。
このように、全体としては史実に忠実ながらも、感情や背景に深みを持たせるため、ドラマならではのアレンジが加えられているのが『べらぼう』の特徴です。
『べらぼう』の徳川家治はこの後どうなる?
第20話では側室で亡くなった家基の母であるお知保の方が自殺未遂を起こします。
それによって家治の気持ちは動いていくのでしょうか?
家治の後継者選び
歴史の流れとしてはこの後老中の田沼意次、若年寄の酒井忠休、そして留守居役の依田政次の3人は、家治より将軍の後継者となるべき養子の選定を任される事になります。
その結果、天明元年の閏5月18日、御三卿の一つ・一橋徳川家の当主である徳川治済の嫡子・豊千代が後継に決定します。豊千代は同年11月2日に「家斉」と名を改め、翌・天明2年(1782年)4月2日には従二位・権大納言に叙任されました。
この豊千代は第2話で生まれたことをお祝いする宴が行われていましたね。この宴で徳川治済と意次が一緒に傀儡を操るシーンがありました。すでにここにフラグが立っていたのです。
この家斉擁立の中心人物とされたのが田沼意次です。将軍・徳川家治は意次の尽力を高く評価し、天明元年7月15日にその功績として1万石を加増しています。
田沼意次の弟・意誠や、その子・意致らが一橋家に仕えていたこともあり、意次と徳川治済の間には事前に深いつながりが築かれていた可能性があるというのです。
こうした人脈が、家斉を将軍継嗣に押し上げるための土台となっていたのかもしれません。
家治の死亡
その5年後家治は50歳でこの世を去っています。
家治は晩年は脚気が悪化し心不全で亡くなったとされますが、
一部では田沼の陰謀による毒殺説もあります。ただし、家治の死後、田沼は急速に失脚しており、毒殺の可能性は低いと考えられています。
家治が亡くなると田沼は失脚、松平定信によって蔦重たちを取り巻く環境は一変していきます。
まとめ|『べらぼう』徳川家治はどんな人?史実の人物像とドラマの違いを徹底解説!
徳川家治は、争いを好まない温厚な性格で、実際には目立った改革を行った将軍ではなかったものの、田沼意次ら有能な側近を支え、比較的安定した治世を築いた人物でした。
一方、ドラマ『べらぼう』では、家治の人間的な優しさや苦悩が強調され、史実よりも感情豊かなキャラクターとして描かれています。この違いは、物語のドラマ性を高めるための演出であり、視聴者に家治の魅力を伝えるための工夫といえるでしょう。
史実とドラマ、それぞれの視点から家治を知ることで、物語をより深く楽しめるはずです。ぜひドラマと史実の両方から、徳川家治という人物を味わってみてください。