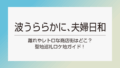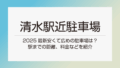昭和の家庭に息づく、懐かしくも知られざるアイテムが『波うららかに、めおと日和』第3話に続々登場しました!
アッパッパ、炭火アイロン、そして瀧昌が手にするスーツの値段など、当時の暮らしをリアルに映し出しています。
「それってどんなもの?」「今と比べて高いの?」と気になった方のために、当時の昭和の暮らしをわかりやすく解説します!
この記事を読んでわかること
- アッパッパとはどんな洋服?その特徴や価格
- 昭和初期の男性用スーツや女性服の相場
- 炭火アイロンや霧吹きの使い方と価格
- 瀧昌の給料から見る昭和の生活水準
【波うららかに、めおと日和】アッパッパってなに?お値段は?
3話では女性の着るアッパッパが出てきました。「なんか聞いたことある」と思った方多分昭和生まれですね。
アッパッパはいつから着られるようになった?
- 明治から大正にかけて西洋文化が日本に入ってきたことで、着物に代わる「洋装」が徐々に女性たちの間でも浸透。
- しかし、当時の洋服はまだ高価で、手入れも難しかったため、庶民にとっては「気軽に着られる洋服」が求められていました。
- そんな中で生まれたのが、アッパッパ。これは、「布をたっぷり使った簡単な仕立てのワンピース」で、直線的なラインと袖付きのデザインが特徴。
名称の由来には諸説あり、「風でふわっとめくれる様子(アッパッパー)」から来ているとも言われています。
アッパッパの特徴
- 前開きやかぶり式で着脱が簡単
- ウエストに締め付けがなく、涼しくて動きやすい
- 綿素材で洗いやすく、家庭での洗濯に適していた
- カラフルな花柄やストライプなど、明るいプリント柄が多かった
アッパッパの値段
- 時代や地域によって異なりますが、昭和30年代当時でおおよそ300〜500円程度だったと言われています。
- 昭和初期の値段は資料が残っていないのですが当時の物価水準を考慮すると、アッパッパは数円から十数円程度の価格帯で販売されていたと考えられます。
- 当時の公務員の月給が約30円〜50円。比較的安かったこと思われます。
\今でもアッパッパで検索すると売っています!/
【波うららかに、めおと日和3話】三つ揃いスーツの値段は?
昭和11年頃、テーラーで仕立てる三つ揃いのスーツ(上着・ズボン・ベスト)は、かなり高価なものでした。
- 一般的な価格帯は40円〜80円程度
- 高級テーラーや舶来生地を使用したものだと100円以上になることも
比較参考:
- 小学校教員の初任給:約40〜50円
- 白米10kg:約3円
- ラジオ一台:約60〜80円
つまり、スーツ一着で月給の1ヶ月分以上するような高級品だったわけです。
高い洋服などを「一張羅(いっちょうら)」として大切にされる理由もうなずけます。
ちなみに昭和初期の女性の服:どこで仕立てた?
それでは女性の洋服はどうだったのでしょうか?昭和30年代ぐらいまで自宅や近所の仕立てのできる人に作ってもらっていたように思います。
1. 自宅での手縫い・仕立て
当時、女性の多くは和服を自分や家族で仕立てるのが一般的でした。母親や祖母から技術を教わるのが普通で、洋裁ができる女性も増えてきていました。
- 地元の呉服屋で反物を買って、自宅で仕立て
- 和裁や洋裁学校に通う女性も増加中
2. 洋服は仕立て屋(洋裁店)で
洋装が広まる中で、**町の洋裁店(仕立て屋)**に注文する人も出てきました。
- 女性用ワンピース:5円〜10円程度
- ちょっとした外出着:10円〜20円前後
- 生地代+仕立て代で、月収の1/4〜1/2くらい
3. 百貨店や仕立て屋の台頭
昭和初期の銀座・日本橋などでは、三越や松屋といった百貨店で既製服や仕立てサービスが始まっており、都市部の中産階級女性を中心に利用されていました。
【波うららかに、めおと日和3話】アイロンは炭火式が主流!霧吹きについても
この時代のアイロンは、まだ電気アイロンは一部の上流家庭のみで、庶民の間では炭火式アイロンが一般的でした。
炭火アイロンはアイロンの中に炭を入れて使うもので見た目は「ふた付きの小さな鉄の箱」のような形。煙突のような穴が空いているものもありました。
炭火アイロン
— 奇貨屋白昼夢 東大阪 布施 昭和 レトロ 雑貨屋 (@hakuchuum_osaka) March 26, 2025
明治〜昭和初期頃に使われていた炭火アイロンです。
炭火を中に入れその熱でシワをのばす為空気穴と煙突がついています。
ズッシリ重たいです。
日の丸のデザインがとても良いですね。
横17.3㎝
高16.5㎝
4000円です。#炭火アイロン#日の丸#炭アイロン pic.twitter.com/wpkP2hI3w3
◆ 炭火アイロンの特徴
- 鉄や真鍮製の本体に炭や豆炭を中に入れて加熱する構造
- 熱を保ちやすく、こてのように重くてどっしりしている
- 持ち手は木製で熱くならない工夫がされている
- 熱の調整は炭の量で行うため、こまめな調整が必要
- アイロンがけ中はパチパチ音やにおいもあった
霧吹き(しぶき器)について
◆ 昭和初期の霧吹きとは
アイロンがけの際に「しわをのばしやすくするため」に、霧吹き器(しぶき器)が一緒に使われていました。
主なタイプ:
- 竹筒式しぶき器(指で水をはじいて霧状にするもの)
- 口で吹いて、空気圧で水を霧状に噴射するタイプ
- ブリキ製のポンプ式霧吹き
- 和紙を丸めた簡易スプレー(自作)も庶民の工夫の一つ
なつ美が使っていたのは口でふいて使うタイプでした。
昭和初期の主婦の友みてるんやけど、アイロンはだいたい20世紀初期には電気アイロンがあったっぽいのに、霧吹きは口なんやっていうさりげない衝撃 pic.twitter.com/HPWxqVVmYB
— モツ15 (@motunabe15) September 9, 2017
◆ 価格の目安
- 簡易的な霧吹き:10銭〜30銭
- ブリキや金属製のしっかりしたもの:50銭〜1円程度
【波うららかに、めおと日和3話】瀧昌の給料はいくら?昭和11年・海軍少尉の月給とは
劇中で登場した「瀧昌(たき・しょう)」は、昭和11年(1936年)当時の海軍中尉という設定。海軍将校には大学を卒業しないとなれません。瀧昌はエリートなんですね。
昭和11年の海軍中尉の月給
昭和10年頃(1935年頃)の帝国海軍中尉の月給は、おおよそ65円〜80円程度とされています。
※参考:『昭和10年の給与体系(帝国陸海軍・官公庁)』
当時の物価を踏まえると、これは今の価値で約25万〜30万円前後に相当。住宅費や食費も現代ほど高くなかったため、家族をしっかり養える収入でした。
昭和11年の職業別・月給一覧
| 職業・身分 | 月給の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 大学新卒の男性(初任給) | 約60円〜70円 | 大手企業・銀行・鉄道・新聞社など。大卒はまだ希少で高待遇 |
| 一般会社員(中卒〜高卒) | 約30円〜50円 | 学歴や職種によって差があり。営業・技術系はやや高め |
| 女性タイピスト | 約25円〜40円 | 官公庁では25円程度、民間では英語対応できれば50円近くも可能 |
| 女給(カフェー・バーなど) | 約20円〜40円+歩合 | 基本給は低めだが、心付け(チップ)や売上歩合で実収入は高くなる場合も |
参考:当時の物価感覚(昭和11年頃)
- うどん一杯:5銭〜10銭
- 白米10kg:約2円〜3円
- 新聞購読料(1ヶ月):50銭前後
ちなみに当時は手取り30円程度あれば、家族を養えるとされていました。
他の職業と比べると少しだけ高収入といえますが、制服、軍刀などの軍装品は自分で用意しなくてはならずお金はかかりました。
スーツを作るとすると安くても月給の半分は飛んでいってしまうのですね。
瀧昌は帝国海軍の中尉で月給は月給は約65〜80円だと推定されます。
現代にすると大体19万円ぐらいと考えられます。
海軍は国家公務員扱いなので安定をしていますが瀧昌はそれほど高給取りではなかったと考えられます。
まとめ【波うららかに、めおと日和】アッパッパとは?瀧昌の給料と昭和の暮らし解説
『波うららかに、めおと日和』第3話では、アッパッパや炭火アイロン、霧吹きなど、昭和のリアルな暮らしが随所に描かれていました。
アッパッパは、庶民に親しまれた涼しくて動きやすいワンピースで、昭和30年代には300円前後とお手頃。
一方、瀧昌が作った三つ揃いのスーツは、月給相当の高級品。
炭火アイロンや手作りの霧吹きなど、今では考えられない工夫が満載だった昭和の家庭用品にも注目です。
現代と比較しながら、当時の生活に思いを馳せてみると、新しい発見がたくさんありますね!
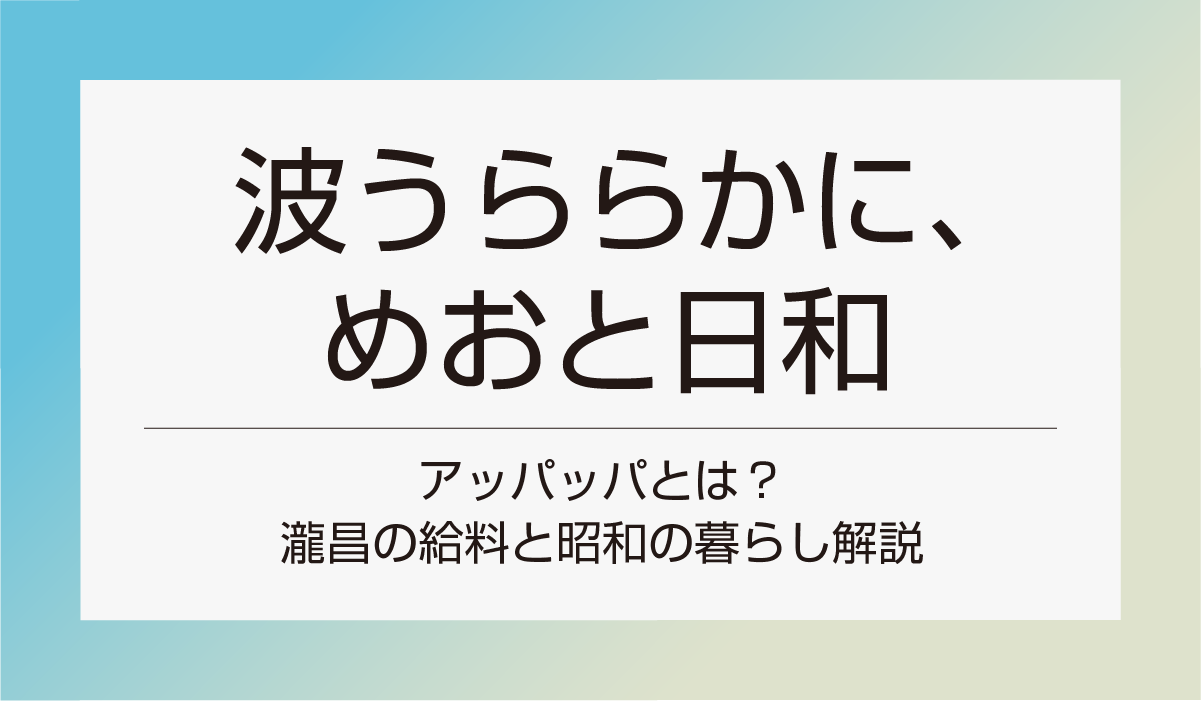
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47e00b87.819baf41.47e00b88.8c98e28d/?me_id=1308803&item_id=10000220&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcottonmatsui%2Fcabinet%2F07169402%2Fcompass1691654115.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)